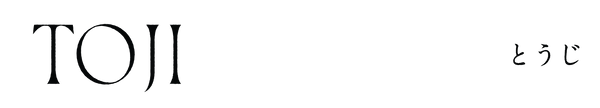TOJI × 酒蔵のストーリー Vol.02|宮坂醸造― 社長室室長編
share
原点へ戻り、ブランドを磨く―継承と新たな挑戦で、真澄の未来を描く宮坂勝彦氏
酒蔵の価値は、酒そのものの味わいだけで語り尽くせるものなのでしょうか。
土地の文化や食卓との関係性、造り手の思想、そしてそれらがどのような言葉や姿で伝えられてきたのか。
長い時間を生き抜く酒蔵には、味わいと同じくらい、一貫した軸が息づいているのかもしれません。
寛文二年(1662)創業、日本酒「真澄」を醸す宮坂醸造。
「協会七号酵母」発祥の蔵として知られる一方で、この10年、真澄は酒質だけでなく、その伝え方や存在の輪郭そのものを、静かに、しかし確かに見つめ直してきました。
その変化を内側から推し進めてきたのが、宮坂醸造 社長室室長の宮坂勝彦さんです。
蔵元の後継として生まれ育ちながらも、宮坂さんはすぐに蔵へ入る道を選びませんでした。
高校時代の海外体験を起点に、アメリカへの留学、伊勢丹での百貨店勤務、ロンドンでの日本酒営業へ。あえて蔵の外に身を置き、異なる価値観や、世界で評価される「良いもの」に触れながら、自分なりの視点を培ってきました。
世界の市場で、日本酒はどう見られているのか。
強い存在は、なぜ選ばれ続けるのか。
伊勢丹の売り場で目にした、美学に裏打ちされた一貫性。ロンドンのレストランで突きつけられた、「この蔵は何者なのか」を瞬時に語る難しさ。
そうした外での経験が、後に真澄と向き合うための、確かな視座となっていきます。
2013年、28歳で蔵に戻った宮坂さんが真正面から向き合ったのは、「真澄らしさとは何か」という根源的な問いでした。
七号酵母への回帰、ロゴの刷新、海外市場を見据えた設計。
それらは新しい価値を足し算するためではなく、原点に立ち返ることで、真澄という存在の強度を高めるための選択だったと言えるでしょう。
本インタビューでは、TOJIの尾嵜が、宮坂勝彦さんに、蔵に入るまでの歩みと外で培われた視点、原点回帰に込めた思想、そして次の10年に向けた組織とその展望について話を伺いました。
杜氏編で語られた「酒造りの原点」と呼応しながら、今回は経営と伝え方の視点から、真澄の現在地を紐解いていきます。
海外に触れた原体験 ⎯ 「蔵を継ぐ」は、いつも意識の中にあった
尾嵜:
まずは、宮坂さんの生い立ちからお伺いしたいと思います。どのような環境で幼少期、学生時代を過ごされたのでしょうか。
宮坂さん:
私は1986年に長野県諏訪市で生まれました。実家は日本酒「真澄」を醸す宮坂醸造で、蔵のある風景は子どもの頃からごく当たり前の日常でした。
幼い頃から、蔵を継ぐことは特別な使命というよりも、「いつかはそうなるもの」という感覚で、自然と意識の中にあったと思います。
一方で、諏訪の外の世界にも早くから目が向いていました。その背景には、父の存在があります。父は、まだ日本酒の輸出が一般的ではなかった時代から海外市場に目を向け、展示会や商談のために頻繁に海外へ出ていました。蔵には海外のお客様が多く、蔵見学のあとに一緒に食卓を囲むこともありました。
そのため「海外」という言葉は、遠い憧れというよりも、日常の延長線上にあるものだったと思います。
高校時代になると、その感覚はより鮮明なものになりました。高校1年生のとき、父に連れられてフランス・ボルドーで開催されていたワインの展示会「VINEXPO」を訪れました。世界中から酒が集まる場所でしたが、その中で日本酒はまだ圧倒的にマイナーな存在でした。
はじめてその場を訪れた自分自身は言葉も通じず、きちんと説明もできない。けれど、その場に立ったことで、「この世界で日本酒を語るには、最低限、言葉が必要だ」という実感が強く残りました。
その想いから、高校3年生のときにAFSの留学プログラムを利用し、1年間アメリカへ留学する決断をしました。行き先はサウスダコタ州の小さな町で、1学年10人ほど。幼稚園から高校までが同じ校舎に集まるような環境でした。
当時は「何もない場所だな」と感じていましたが、大人になってから再びその町を訪れたとき、人と人との距離が近く、土地と暮らしが地続きであることの豊かさに初めて気づきました。この経験は、後に「土地に根ざした酒とは何か」を考えるうえでの土台になっていると思います。
「一度、外から日本を見る」⎯ 真澄に入る前の選択
尾嵜:
大学卒業後、すぐに蔵へ入らず、あえて外で経験を積むことを選ばれた理由を教えてください。
宮坂さん:
いずれ蔵を継ぐからこそ、外で学ぶ必要があると考えていました。就職先として選んだのは、株式会社伊勢丹(現・株式会社三越伊勢丹)です。
得意先の子弟を一定期間預かり育てる、いわば丁稚奉公のような制度があり、そこで2年間、百貨店の現場に身を置きました。1年目は婦人服、2年目は食品を担当しましたが、売り場には価格帯も世界観も異なる多くのブランドが並び、それぞれが明確な哲学や美意識を持っていました。
その中で特に強く印象に残ったのが、「強いブランドほど、美学に基づいた一貫性のあるものづくりをしている」という点です。この気づきは、後に真澄のブランドを考えるうえで、非常に重要な視点となりました。
伊勢丹を退職した後は、ロンドンへ渡りました。日本酒を扱う商社に所属し、現地のレストランを回りながら、料理や価格帯に合わせて酒を提案する仕事に携わっていました。ワイン文化が圧倒的に根付いた市場の中で、日本酒をどのように伝えるのか。営業の現場では、限られた時間の中で「この蔵は何者なのか」を短く、的確に伝えることが求められます。
当時の真澄は、さまざまなタイプのお酒を造っていました。洋服に例えるなら、ドレスからカジュアルな服まで幅広く揃えているような状態です。その分、一言で「真澄のお酒はこういう酒です」と表現することが、正直とても難しかった。
2013年、28歳で蔵に入ったときに強く感じたのは、真澄はいい酒を造ってきたけれど、どこを目指している酒なのかを、誰にでも説明できる状態ではなかったということでした。真澄は長く良いものづくりを続けてきましたが、当時の私には、アイテムによって目指す方向が少しずつ異なって見えたのです。
このままではいけないと強く思ったのは、蔵の外で日本酒を見続けてきた経験があったからこそでした。その違和感は、時間が経つほどに、よりはっきりとしたものになっていきました。

2013年、ロンドンにて日本酒を真澄を紹介する様子
転換点はお寿司屋さんでのペアリング⎯ 七号酵母に立ち返った理由
尾嵜:
真澄の原点回帰の中でも、「七号酵母への回帰」はとても象徴的だと感じています。その転換点について、教えてください。
宮坂さん:
きっかけは「ネタごとにペアリングしてみたら?」という、ある寿司屋さんでの一言でした。実際に休みの日に自分たちの酒を何本か持ち込んで、試してみたことがあったんです。
マグロにはこれ、白身にはこれ、というふうに合わせていったんですが、意外なことに、真澄の酒が一番しっくりきたのは、寿司のネタそのものではなく、途中で出てきた“たくあん”でした。ごぼうの漬物や、そういった保存食にも、すごく相性がよかった。
そのとき、はっと気づいたんです。
海沿いの地域と、内陸の地域では、そもそも食文化が違う、と。
石川や福井、宮城のように海が近い地域では、新鮮な魚が日常にあります。そういう土地で生まれた酒が、魚介と相性の良いのは、とても自然なことです。一方で、長野は内陸です。日々の食卓にあるのは、野菜、味噌や漬物、そして肉。
だとしたら、無理に寿司に合う酒を目指すのではなく、この土地の食文化に根ざした酒を突き詰めるべきなんじゃないか、と思ったんです。
以前は、コンテストで評価されることも大きな目標でした。そうなると、一口飲んで華やかで、印象に残る酒のほうが強い。実際、そういう価値観が業界全体にもあったと思います。
一方、七号酵母はどちらかというと“地味”な存在です。派手な香りで主張するタイプではない。
それでも、真澄の軸に据えるなら、やはり七号酵母しかない。
内陸の食卓に寄り添い、毎日の料理と一緒に飲み続けられる酒。その姿を一番素直に表現できるのが、七号酵母だと改めて認識しました。

尾嵜:
とはいえ、「七号酵母への回帰」を進めていくうえで、社内の合意形成は決して簡単ではなかったのではないでしょうか。
宮坂さん:
簡単ではなかったですね。2013年に蔵へ戻ってからの最初の3年間は、ずっと葛藤していました。当時、私が「七号酵母に戻したい」と伝えても、すぐには受け入れてもらえませんでした。
理由はいくつもありましたが、大きかったのは、当時の現場に「売れているものに合わせていく」という発想があったことです。都内で売れている酒、海外で評価されている酒。そうしたトレンドに寄せてアイテムをつくっていくやり方は、短期的にはわかりやすく、決して否定できるものでもありません。
ただ、私の目には、その積み重ねによって次第に真澄はどこを目指しているのかが見えにくくなっていくように感じられました。その違和感が、どうしても拭えなかったのです。
そして、焦りもありました。いきなり全部を変えようとしても反発が出ますし、何より「七号酵母に戻すこと」が目的になってしまうと、本来の意図からズレてしまう。私がやりたかったのは、七号酵母という“手段”を通じて、真澄の味わいと軸を取り戻すことだったんです。
そこでまず、提案の形を変えました。
全部を七号酵母に戻すのではなく、七号酵母を核にした新しいコンセプトを、まず一本立ち上げる。いわば社内にとっての“実験線”をつくったんです。それが「MIYASAKA」シリーズでした。
MIYASAKAは、全量を七号酵母で仕込みながら、古いものを守るだけのクラシックではなく、今の技術や感覚を使って、モダンな味わいに仕上げています。
「七号酵母=地味」という固定観念に対して、七号酵母でもここまで表現できるんだ、という“再定義”を狙いました。要するに、言葉で説得する前に、味で納得してもらう道を選んだのです。
そうこうしているうちに、少しずつ社内の空気が変わっていきました。
現場から「七号の酒、うまいね」という声が出てくるようになって、七号酵母の方向性が理想論ではなく、現実の手応えとして共有され始めたんです。そこまで来ると、議論の焦点は「戻すべきかどうか」ではなく、「どうやって七号酵母で真澄らしさを磨いていくか」に移っていきました。
結果として、思っていたより早く、2019年の酒造りから全量を七号酵母にすることができました。
今振り返ると、あの3年間は長かったです。でも、そこで時間をかけたからこそ、単なる製造方法の変更ではなく、真澄というブランドに一本の芯が通った感覚があります。
七号酵母に立ち返ることで、真澄が何者なのかを、ようやく自分たちの言葉と酒で語れるようになった——そんな転換点だったと思います。

世界基準で語られる酒へ ─ ロゴ刷新という必然
尾嵜:
真澄のロゴが変わった背景には、やはり海外視点が大きかったのでしょうか。
宮坂さん:
そうですね。かなり大きかったと思います。
前提として、日本はこれから確実に人口が減っていきます。国内市場だけを見ていては、売上を維持することは難しい。そう考えると、海外市場をどう伸ばしていくかは、避けて通れないテーマでした。
ただ、海外で酒を売る中で、ずっと引っかかっていたことがあります。それが「漢字の壁」です。欧米では、ほとんどの人が漢字を読めません。どれだけ歴史やストーリーがあっても、まず名前が読めない、覚えられない。そうなると、選択肢にすら上がらないという現実がありました。
だからこそ、漢字に依存しないかたちで、視覚的に“覚えてもらえる”マークが必要だと感じたんです。
それは、日本らしさを捨てるということではありません。むしろ、言葉が通じなくても、真澄という存在が認識されるための“入口”をつくる、という感覚に近かったと思います。
当時、ワインの世界を見ていても、ラベルデザインは大きく変化していました。
産地名や造り手の思想を長い文章で説明するのではなく、動物やシンボル、数字など、言葉が読めなくても直感的に認識できる「記号性」を強める流れがありました。
古いクラシックなデザインもありますが、より世界でどう見られるかを意識したアップデートが進んでいた。
真澄も、同じフェーズに来ていると感じました。
七号酵母への回帰で、酒の中身には一本芯が通った。であれば次は、その芯をどう外に伝えるか。その答えのひとつが、ロゴの刷新だったんです。
新しいロゴは、漢字が読めなくても認識できる形でありながら、真澄の持つ静けさや品格、長い歴史を損なわないことを意識しました。
派手に主張するためのデザインではなく、世界のどこにあっても、「これは真澄だ」と分かるための設計です。
ロゴを変えたことで、酒そのものが変わるわけではありません。
ただ、世界と向き合うための言語を一つ増やした、という感覚はあります。
中身と外見、その両方がようやく同じ方向を向き始めた——そんなタイミングだったと思います。

※宮坂家の家紋である蔦。逞しく這い上がり葉を茂らせる蔦は古来繁栄の象徴でした。水鏡や酒盃に映り込んだ蔦の葉を、蔵人が重んじる「和醸良酒」の和=輪の形状に仕立てました。ブランドメッセージ「人 自然 時を結ぶ」に含まれる伝統と革新の二面性、七号酵母の穏やかで調和のとれた風味、世界へ向けた酒文化の発信といった想いが込められています。
国内市場の再構築 ⎯ 「好きで飲む人に選ばれる品質」へ
尾嵜:
海外比率が伸びる一方で、国内は酒離れも進んでいると思います。国内市場をどのように捉えていますか。
宮坂さん:
国内の売上が減っているのは、間違いないです。コロナの影響もありましたし、飲食の場そのものが変わりました。
ただ、それを「人口が減ったから」で片づけたくはないんです。人口動態は事実としてあるけれど、それだけを理由にしてしまうと、こちらが考えることを放棄してしまう気がしていて。
もっと本質的には、「日本酒の飲み方」が変わってきていると感じています。
これまでの時代は、どちらかというと付き合いで飲むシーンが大きかったと思うんです。上司に合わせる、場に合わせる、断りにくいから飲む。そういう飲み方が社会の中に一定あった。
そうなると、極端な話、美味しいかどうかよりも、安いことや量が確保できることが優先されてしまうこともあるわけですよね。
でも、これからはその構造が変わると思っています。
無理に飲まされる人は減っていく。一方で、残るのは「好きで飲む人」です。体質もありますし、そもそも飲めない人もいる。飲まない選択が当たり前になっていく中で、それでも飲む人は、好きだから飲む。その人たちに選ばれ続けるためには、今まで以上に品質が問われるようになると思います。
ここで言う品質は、単に派手で分かりやすい美味しさだけではないんです。
飲み飽きしないこと、食卓の中で自然に寄り添うこと、二杯目、三杯目がちゃんと美味しいこと。そういう持続する良さが、むしろ重要になっていく。
好きで飲む人ほど、そういうところを見ていますし、正直ですから。
だから国内市場を立て直すというのは、広告を打って一気に広げる、というよりも、もう一度「真澄は何のための酒なのか」という選ばれる理由を丁寧に積み上げていくことだと思っています。
七号酵母への回帰や、ブランドの芯づくりっていうのも、結局はそこにつながっているんですよね。派手さで勝つというより、好きな人にちゃんと選ばれる酒にする、ということです。
もちろん簡単ではないです。飲む人と飲まない人がはっきり分かれていくからこそ、母数は減っていく。でも、その中で真澄を選んでくれる人にとって、期待を裏切らない品質を出し続ける。
国内はその勝負になると思っています。
酒粕活用と“体験”の価値 ⎯ 飲めない人にも開かれた酒蔵へ
尾嵜:
酒粕を使った入浴剤の話を最初はどう思われましたか。
宮坂さん:
最初に話を聞いたときは、率直に面白いと思いました。酒粕もこれからは今までと同じようには売れない時代になっていますし、酒蔵としても、副産物をどう活かしていくかは避けて通れないテーマだからです。酒粕には発酵食品としての価値もありますし、食べる以外の用途に広がっていくのは自然な流れだと思いました。
ただ一方で、正直、不安もありました。
過去には化粧品開発も検討したことがありましたが、差別化の設計が難しかったり、社内でも「人の肌につけるものは専門外」という声が出たり、仮に品質面で何かあったときに真澄のブランドに影響が出ないか、という懸念もありました。
今回TOJIの皆さんがゼロベースで始めると聞いて、どこまで実現できるのかが最初は未知数でしたが、実際に形になったものを見て、とても驚きました。
パッケージデザインも、商品の中身も、すごく良かった。価格帯も含めて「この価値に対して、この価格なら納得できる」という設計になっていたんです。単に話題性で売るのではなく、ちゃんとプロダクトとして成立している、そこに誠実さを感じました。
そして、売り出してみたら、きちんと売れた。
机上のアイデアではなく、実際にお客様が選んでくれた。そこではじめて「これは真澄にとっても、新しい可能性になる」と思えました。
正直、皆さんがいなかったら、私たちはこういう領域に繋げることは難しかったと思います。酒蔵だけで考えていたら出てこない発想だし、踏み出す勇気も持てなかったかもしれない。外部の人と組むことで、初めて生まれる価値があるんだなと感じました。
さらに大きいのは、ここから先の「体験」の話です。
ワイナリーの世界を見ていると、最終的には世界中のファンがその場所に来て、食べて、泊まって、過ごして、その土地ごと好きになる。そういう形でブランドが育っているところが多い。そこには必ず“体験”があります。
酒蔵もこれからは、ただ酒を造って出荷するだけではなく、いかに「来てもらって体験してもらうか」が重要になっていくと思っています。
そして、その体験は「お酒を飲める人」だけのものではないはずです。飲めない人にも開かれていること。飲まなくても、その土地の文化や発酵の魅力、酒蔵の時間の流れを感じられること。そういう設計ができるかどうかが、伝統産業が次の20年、30年を生き残っていく上で、とても重要になると思います。
酒粕の活用は、その入口としてすごくいい。
“飲む”以外の接点をつくることで、酒蔵の価値がより多くの人に届くようになる。そういう意味でも、この取り組みは、単なる新商品開発以上の意味があると感じています。
次の10年は「枝葉」を育てる ⎯ 一本の軸の上に自由度をつくる
尾嵜:
最後に、これからの真澄について、どのような未来を思い描いていますか。
宮坂さん:
難しい質問ですね。
ただ、いま自分の中で強く思っていることが二つあります。
一つは、社員がもっと酒造りや、酒を売ることを“楽しめる”状態を増やしたい、ということです。今もみんな真面目にやっていますし、やる気はあります。でも、もう少し「面白いからやる」「もっと良くしたいから試す」という前向きなエネルギーが、現場の空気として当たり前に循環する状態にしたいんです。
そのためには、挑戦できる土壌を用意しないといけない。失敗しても学びにできる仕組みや、提案が出てくる余白、挑戦が評価される文化、そういうものがないと、結局、人は守りに入ってしまいますから。
もう一つは、真澄というブランドの次の成長の形です。
この10年は、七号酵母への回帰をはじめとして、一本の大きな軸を通してきました。正直に言うと、あれはある意味、僕のエゴで押し切ってきたところもあります。「真澄はこうあるべきだ」という強い意思を、酒にも、言葉にも、ブランドにも、寄せていった。
ただ、当然ですけど、僕一人でできることには限界があります。
一本の軸が通った今こそ、そこからどんな枝葉が生えてくるのか。そこを、もう少し自由度を持って、みんなに任せていきたいと思っています。
ここで言う“枝葉”は、単に新しい商品を増やすとか、企画を増やすとか、そういう意味だけではありません。
味わいの表現の幅かもしれないし、届け方かもしれないし、体験のつくり方かもしれない。あるいは、働き方やチームの在り方そのものかもしれない。真澄らしさという一本の軸があるからこそ、そこから伸びる枝葉は、むしろ強くなるはずだと思うんです。
ただ、難しいのは、「自由にやっていい」と「何でもやっていい」は違う、ということです。
真澄らしさを守るためには、線引きが必要になる。でも、その線を引きすぎると、今度は枝葉が育たない。逆に自由にしすぎると、軸がぼやける。
そのバランスをどう取るかが、次の10年の一番難しいテーマだと思っています。
だからこそ、まずは“軸”を共有することが大事なんですよね。
真澄が何者で、どんな価値を届けたいのか。その共通言語が皆に腹落ちしたうえで、それぞれが自分の枝を伸ばせる状態をつくる。
次の10年は、そこに挑戦していきたいと思っています。

最後に
前回の杜氏編で、那須さんが語ってくれた「和醸良酒」——
和の中から酒は生まれる、という思想。
今回、宮坂勝彦さんの言葉から浮かび上がってきたのは、その“和”を、酒造りの現場だけでなく、ブランドや組織の側からどう育て直していくのかという視点でした。
七号酵母への回帰によって一本の軸を定め、世界で伝わるかたちへと整える。
そして次の10年は、その軸の上に、さまざまな枝葉を伸ばしていく。
酒の味わい、伝え方、体験のあり方、そして人。真澄というブランドは今、静かに広がりを持ちはじめています。
「真澄らしさ」を守ることは、決して立ち止まることではありません。
変わらないためではなく、変わり続けるために立ち返る場所を持つこと。
その覚悟が、真澄という酒の現在地を形づくっているように感じられました。
静かに、しかし確実に。
真澄はこれからも、その一本の軸を確かめながら、次の時代へと歩みを進めていきます。
(書き手:尾嵜未依)